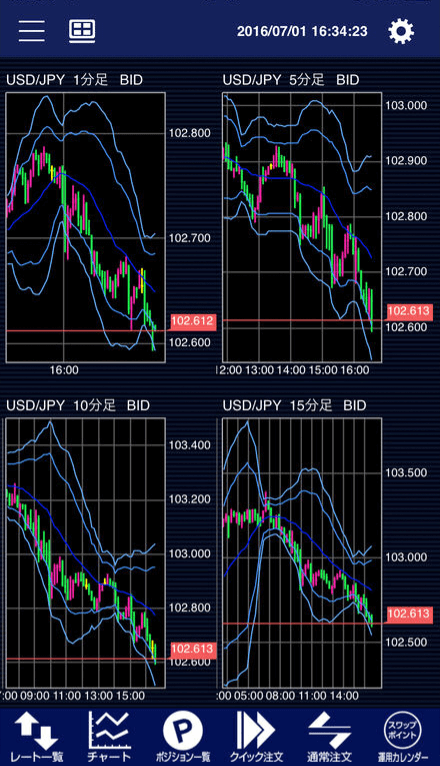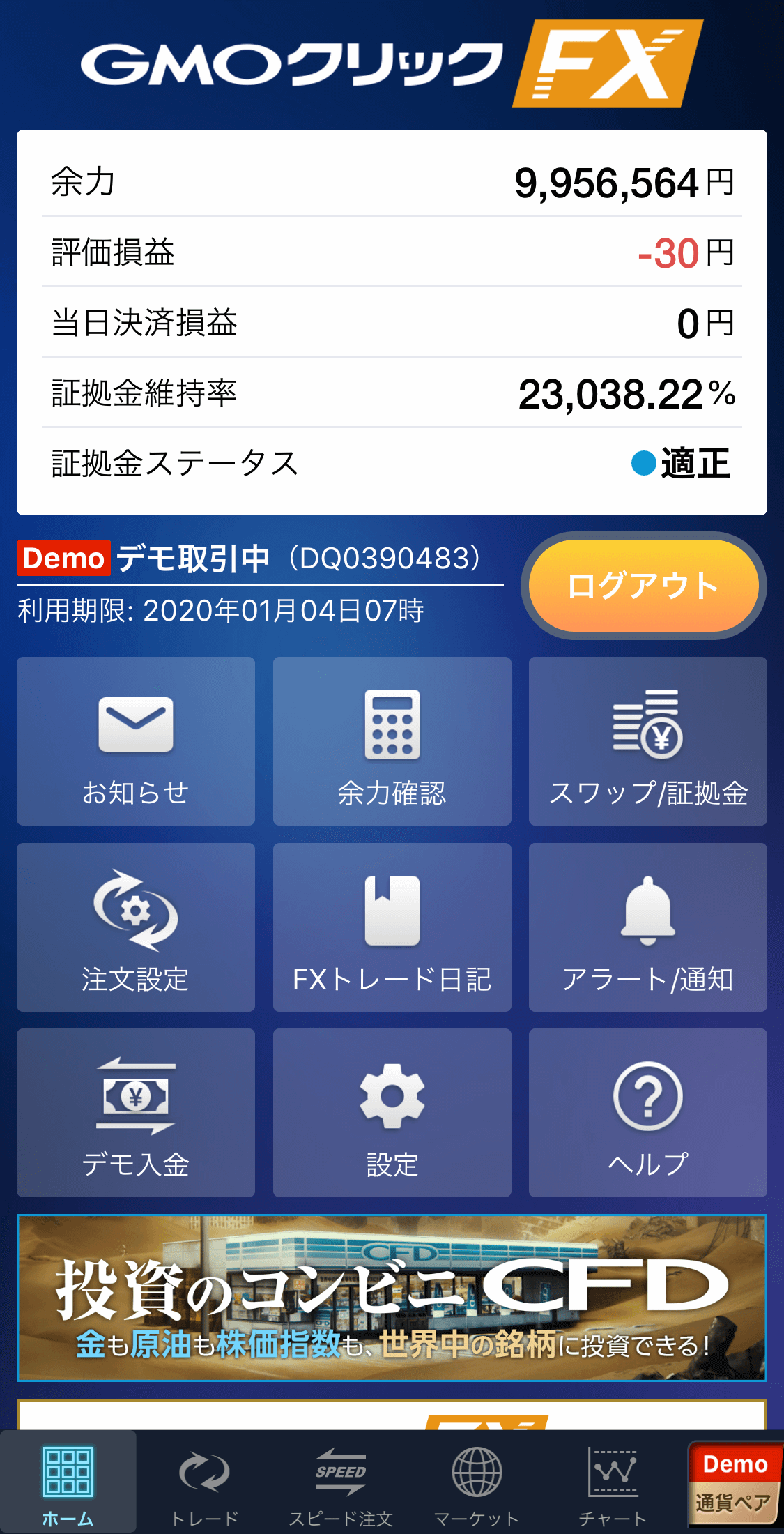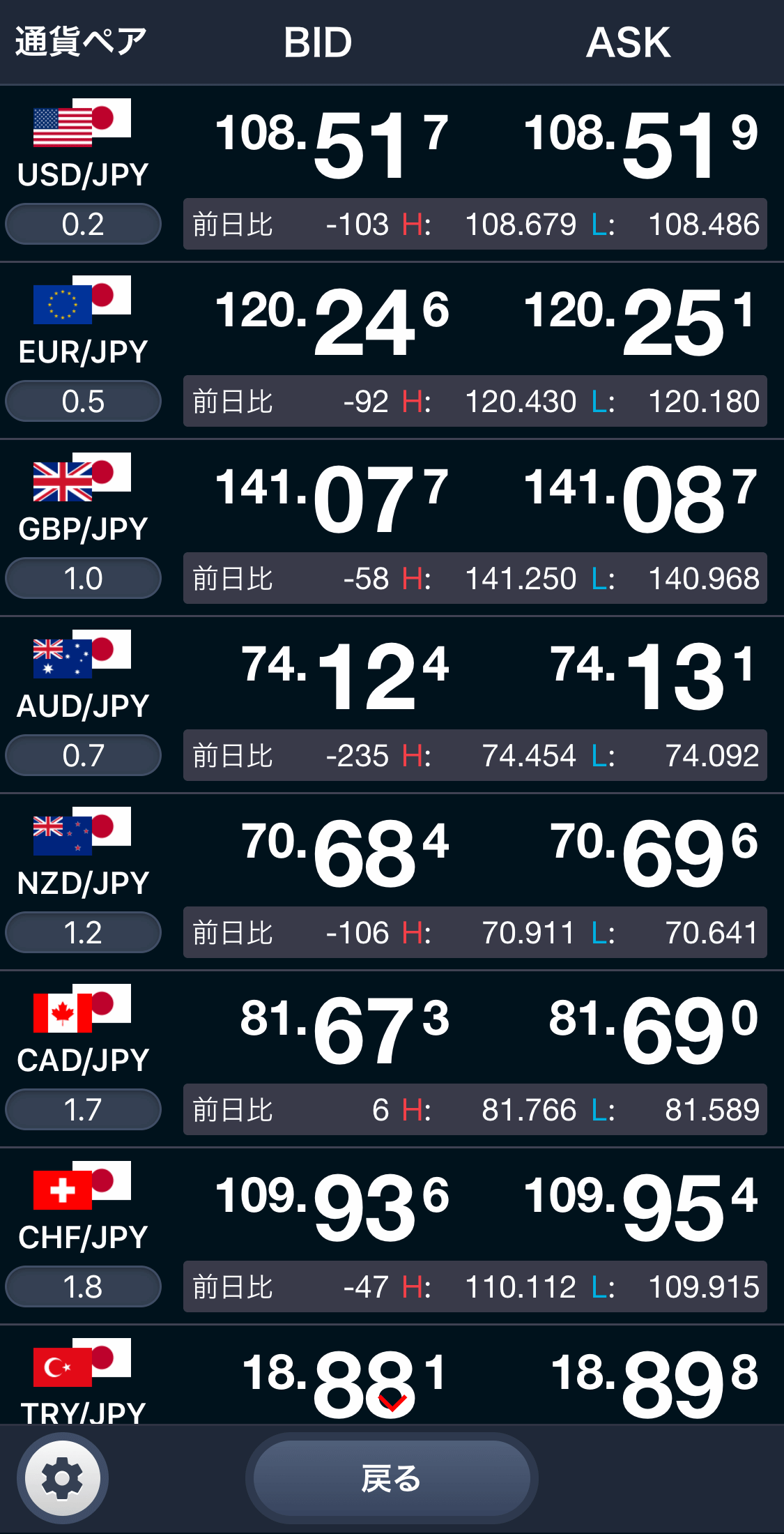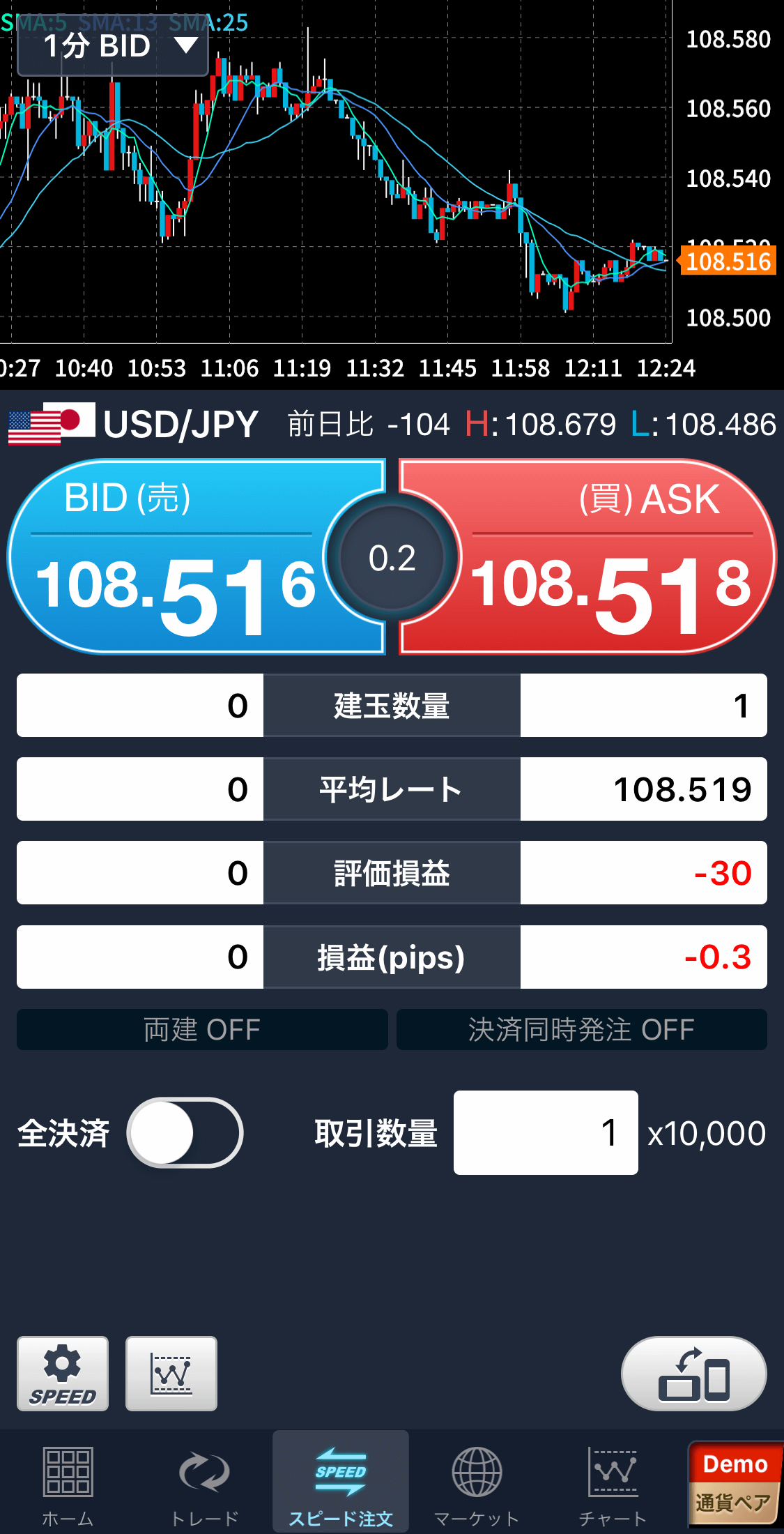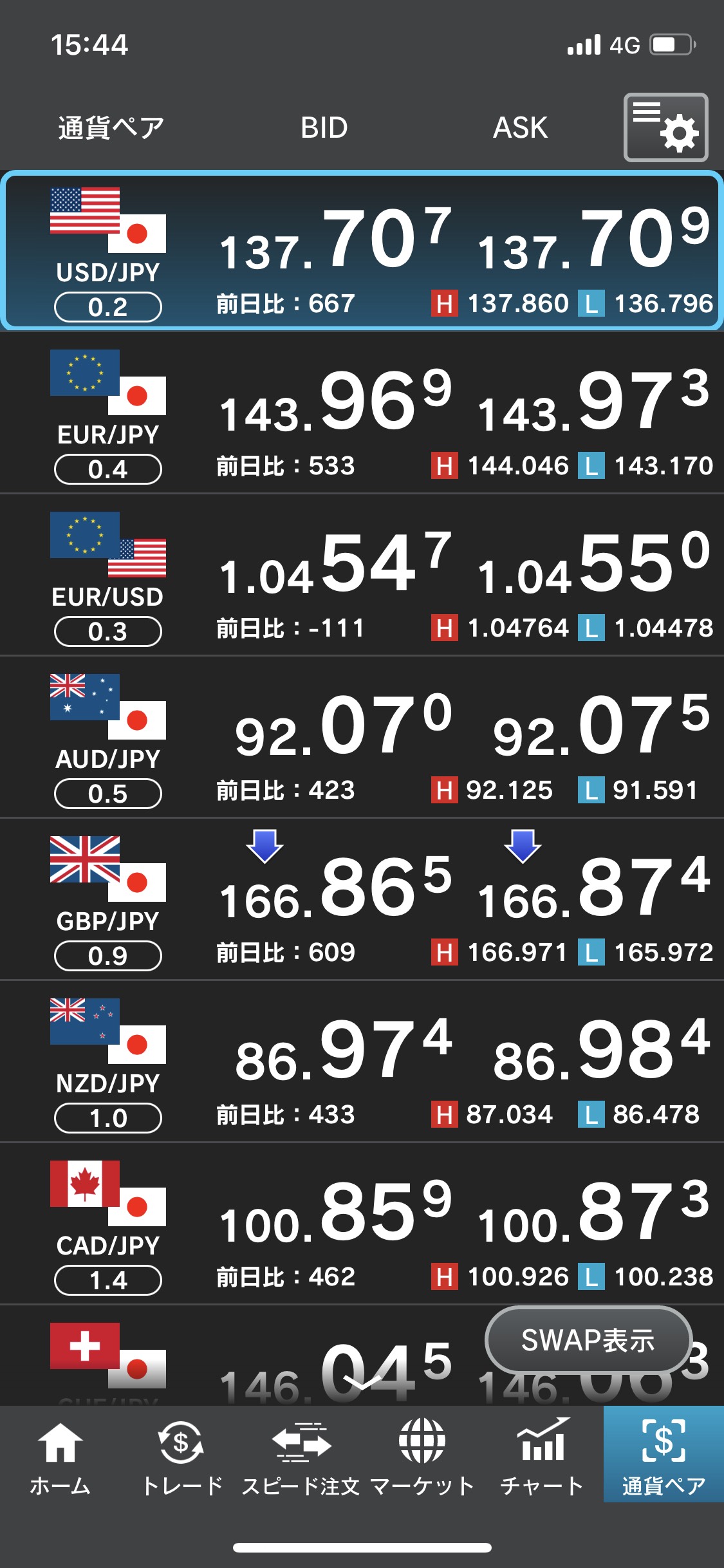予想外にしぶとく上昇する日経平均
変わらないのは、半導体の強勢
日経平均は、思った以上に元気な一日でした。
これといって柱が定まらない散漫な物色動向でした。エーザイ<4523>やサンバイオ<4592>、あるいは中外製薬<4519>が牽引した薬品が業種上昇率ランキングの上位になっていたくらいですから、中身が無い相場であったことは一目瞭然。
ただ、その中にあっては、相変わらず半導体が強勢を示していました。昨晩のラムリサーチ<LRCX>の決算に続き、重鎮インテルがやはり引け後に決算発表。これが最高益ということで、アフターマーケットでは気配が4%近い切り上げとなっていたことが要因だったようです。
東証一部上昇率ランキング上位も上位、トップのほうに、7000億円以上もある時価総額のディスコ<6146>が台頭し、10%の上昇をするというのも驚きです。
上昇率ランキング上位には、ディフェンシブ・シクリカル混在ですので、なんともこれでは方向性はわかりませんが、一応シクリカルが強勢を張っているわけなので、これが指数を押し上げていると言うことで良いのでしょう。
相変わらず、ソフトバンク<9434>とファーストリテイリング<9983>が安いのですが、先述のエーザイ<4523>や東京エレクトロン<8035>、アドバンテスト<6857>などが指数のプラスの寄与度に貢献しています。
指数プレイの裁定買い残積み上げというよりは、個々のピックアップ=アクティブ運用が主体なのでしょう。
日経平均終値は、49円高の22,799円です。
「株の売り手不在」の問題~やはり11月7日に、警戒を厳とする
本日の日経新聞朝刊「スクランブル」には、株高に対する警鐘が解説されています。
ポイントは、売り手がいないという事実です。
(VIXの空売り残の膨張)
日本のVIX指数の空売り残は増えてきていますが、これは相場の急変動が無いとみる投資家が、VIXを売り持ちを拡大させているということです。
この枚数が記事によれば、売り越し高10万枚が分岐としています。過去、2018年10月、19年5月の相場急落の直前に、いずれも10万枚を超えていたことを指しているわけです。
では、どこで相場急変動が起こるのでしょうか。現在上昇している日経平均が急変動するということは、急落するということを意味しているわけで、そのタイミングはいつだろうか、ということです。
(裁定売り残はピークアウトで、減少中)
たとえば、日本の日経平均先物の裁定取引の売り残高は9月初めに2兆円をピークとして、減少しつつあります。
つまり、裁定売りの解消が進んでいるわけで、これが根本的にこのところの日経平均上昇の原動力です。けっして、実弾による買い方の押し上げパワーではなく、空売り筋のショートカバーです。
上がっているといっても実態はそのていどの上昇相場にすぎないのです。
(裁定売り残解消が終わる時、相場上昇が終わる)
そうなりますと、この裁定売りの解消が終息するのはいつか、ということが問題になってきます。
9月6日までの週間で、売り残は2兆666億円。これが、ピークだったわけですが、その後以下のように、直近まで減少中。10月18日には、1兆5,388億円に減少。
2017年まで遡ってみますと、この裁定売り残ピークと、日経平均ボトムがほぼ相前後していることが確認できます。
ざっくりとした数字ですからおおよそなのですが、以下の通りです。
裁定売り残ピーク2017年9月ごろ約7,000億円で、日経平均9月にボトム
裁定売り残ピーク2018年4月ごろ約1兆3,000億円で、日経平均3月にボトム
裁定売り残ピーク7月ごろ約9,000億円で、日経平均7月ボトム
裁定売り残ピーク11月ごろ約8,000億円で、日経平均12月ボトム
裁定売り残ピーク2019年4月ごろ約1兆2,000億円で、日経平均3月ボトム
非常にラフな比較ですが、おおむね裁定売り残ピークと日経平均の突っ込みのボトムが相前後していることがわかります。
(試算すると、相場上昇=裁定売り残解消一段落は11月8日)
2兆円超えという、前代未聞の裁定売り残の多さは、日銀がらみであるという説が強く、異常事態・異常値であるようですが、それにしてもこれが解消され終わるまで、相場は基本的には上昇基調を維持するはずです。
従来の1兆円前後まで解消したとします。過去平均して1兆円くらいが裁定売り残のピークだったと考えると、いくらなんでもそこまでは解消が進むだろうとすれば、そこまで解消する間は上げ相場。そこで相場急落ということはありえます。
もちろん、もっと解消が進んで、従来の裁定売り残の3,000億円から4,000億円くらいまで縮小するかもしれませんが、それはとりあえず横に置いておき、従来の裁定売り残ピークの1兆円くらいまではいくらなんでも縮小するだろう、と考えてみましょう。
すると、今の解消ペースでいきますと、9月6日から10月18日までの21日営業日の間、1日平均で251億円の解消です。
1兆円まで解消するとしたら、ほぼ同じ21日営業日の経過が必要です。
18日から21日後というと、11月8日です。裁定売り残解消が終息すれば、相場は急落することも十分ありうるので、ここが警戒を厳となせという意味になります。
(日経平均、日柄リズムでは次の転換日は11月7日)
これは、従来当レポートで述べてきた、日経平均の天底の日柄リズム22日から試算した、次の小天井は11月7日としたタイミングと1日のズレしかありません。
そこは、1日の雇用統計から8日のSQの間、つまり月間で一番下げ易いアノマリーの1週間に当たります。
従って、ここからはポジション管理が要注意だということになってきます。
もしそこで、日経平均が何らかの材料で急変動(急落)した場合、記事が指摘するVIX空売り残が10万枚を超えピークを迎える動きになってきているので、これが一斉に買い戻しになるわけです。つまり、プットが急増するということと同軌するはずです。
こういった急変動にまで発展するかはわからないものの、警戒は厳としなければならないでしょう。
数量と価格の関係~建設・住宅市況の懸念
本日の日経新聞朝刊には、建設・住宅市況の懸念につながる記事が二つありました。
9月の中古マンションは、都心部の売り出し価格が初の8,000万円台に上昇。
一方で、建設用鋼材が一段安というものです。
ここで、景気というものの基本を押さえておきましょう。
基本的に、景気というのは、「数量X価格」です。
そして、数量が先に動きます。価格はそれによって時間差で突き動かされます。
この記事を二つ並べてみたときに、考えつかなければならないのは、素材の需要が減っていて、最終的な「製品」であるマンション価格が上昇しているという点です。
素材価格が下がるということは需要が減っているからにほかならず、オリンピック需要が今年の春に一巡したことから見て、数量の減退が進んでいるということが容易に想像できます。
最終的にマンション価格にもその流れは反映されてくるはずですから、建設・不動産、住宅といったカテゴリーの銘柄は、今後取り扱い注意だという判断ができます。
実際にどうなるかは、また別の話です。
景気ですから、政策発動などでにわかに盛り返してくるということは当然あるでしょう。
ただ、自然体であれば、投資対象としては今後敬遠しておきたい部類だという結論になるわけです。
戦略方針
日経レバレッジETF<1570>を引き続きホールド続行中です。
執筆者 : 松川行雄|有限会社増田経済研究所 日刊チャート新聞編集長
大和証券外国株式部勤務の後、投資顧問業を開業。2013年2月ヘッドハンティングにより増田経済研究所に入社。現在同社発行の「日刊チャート新聞」編集長。株式セミナーに於ける投資理論は個人投資家に満足度100%の人気を博す。