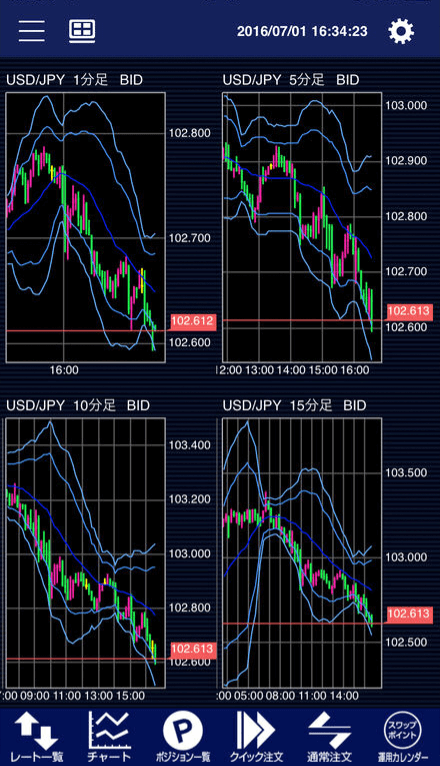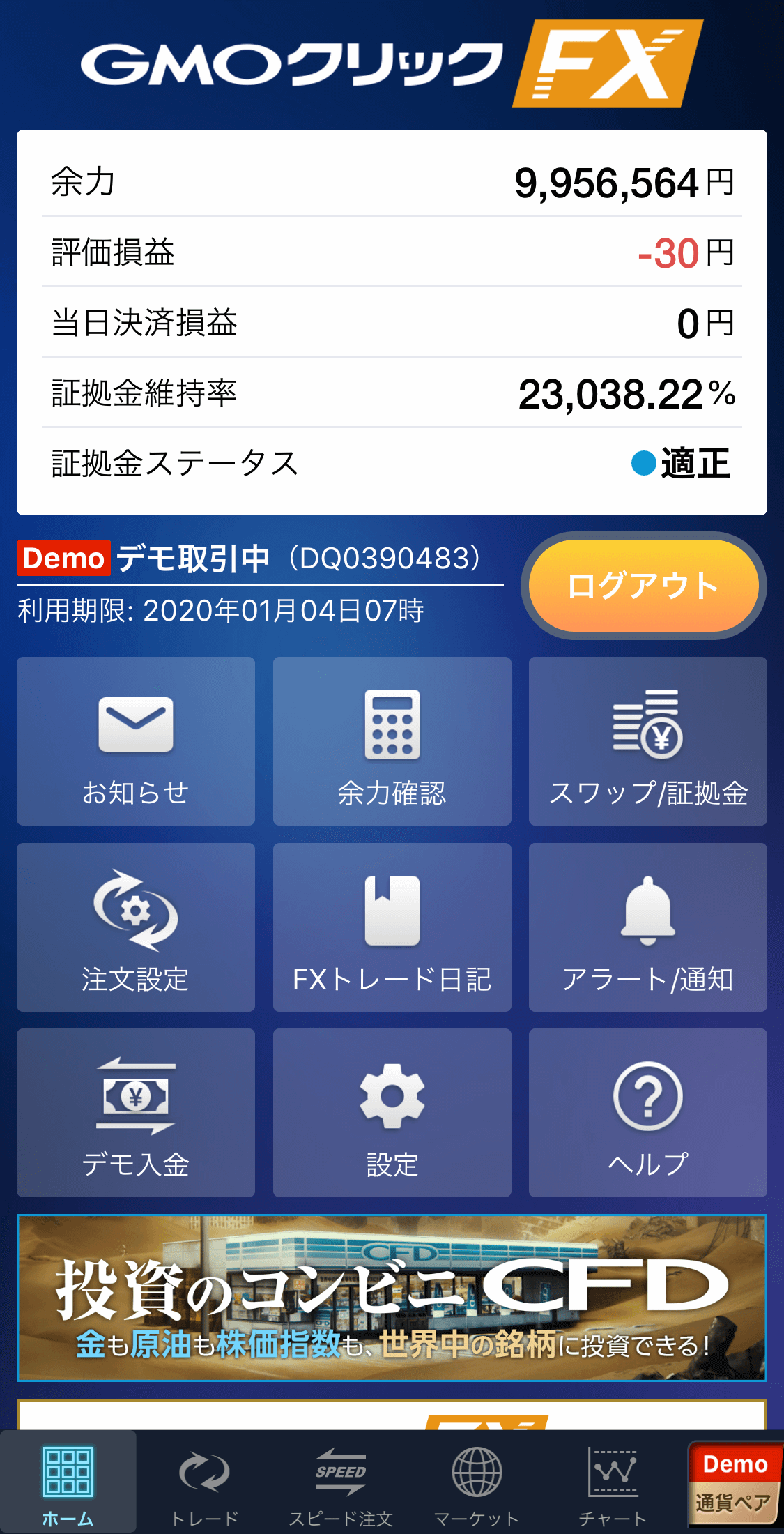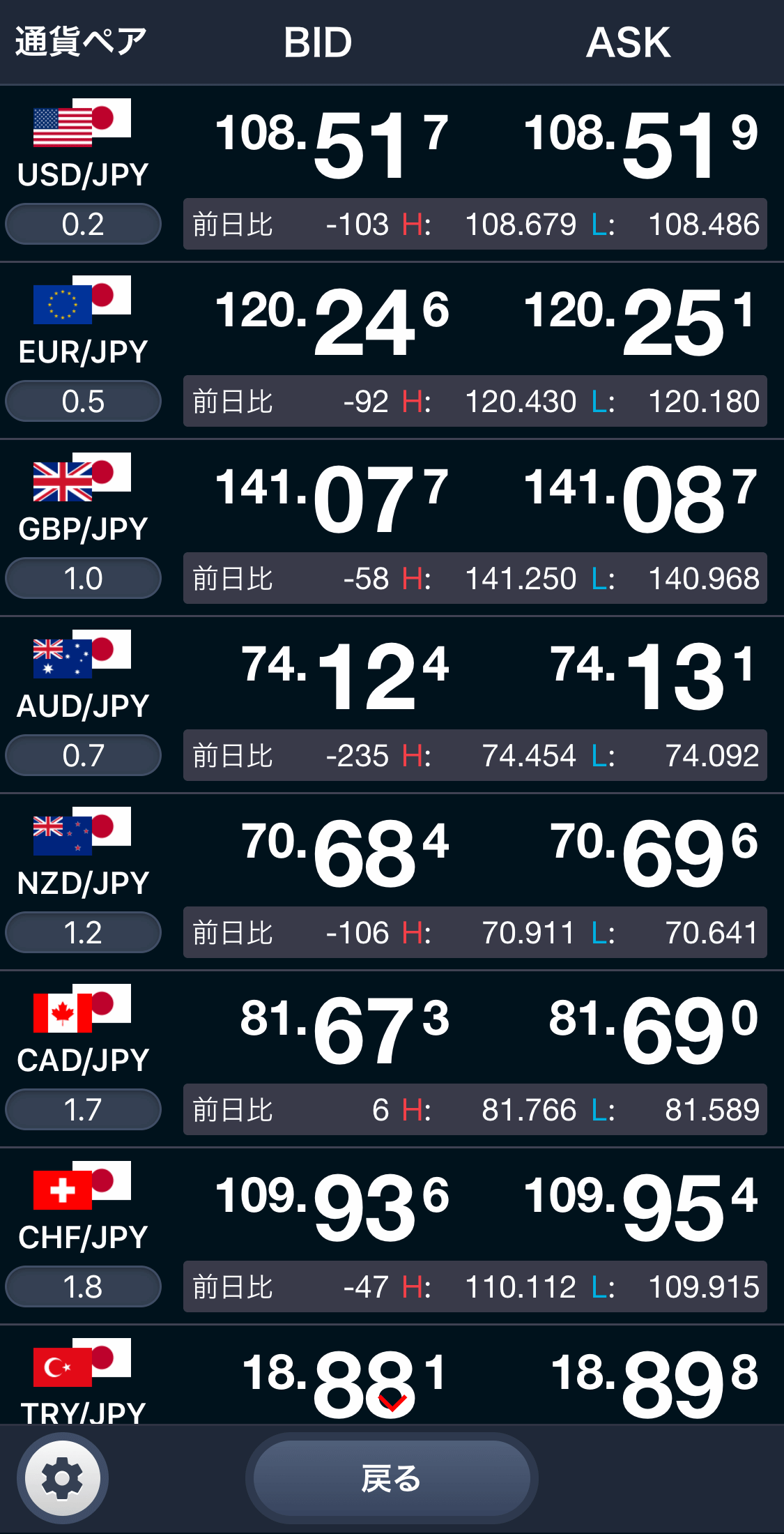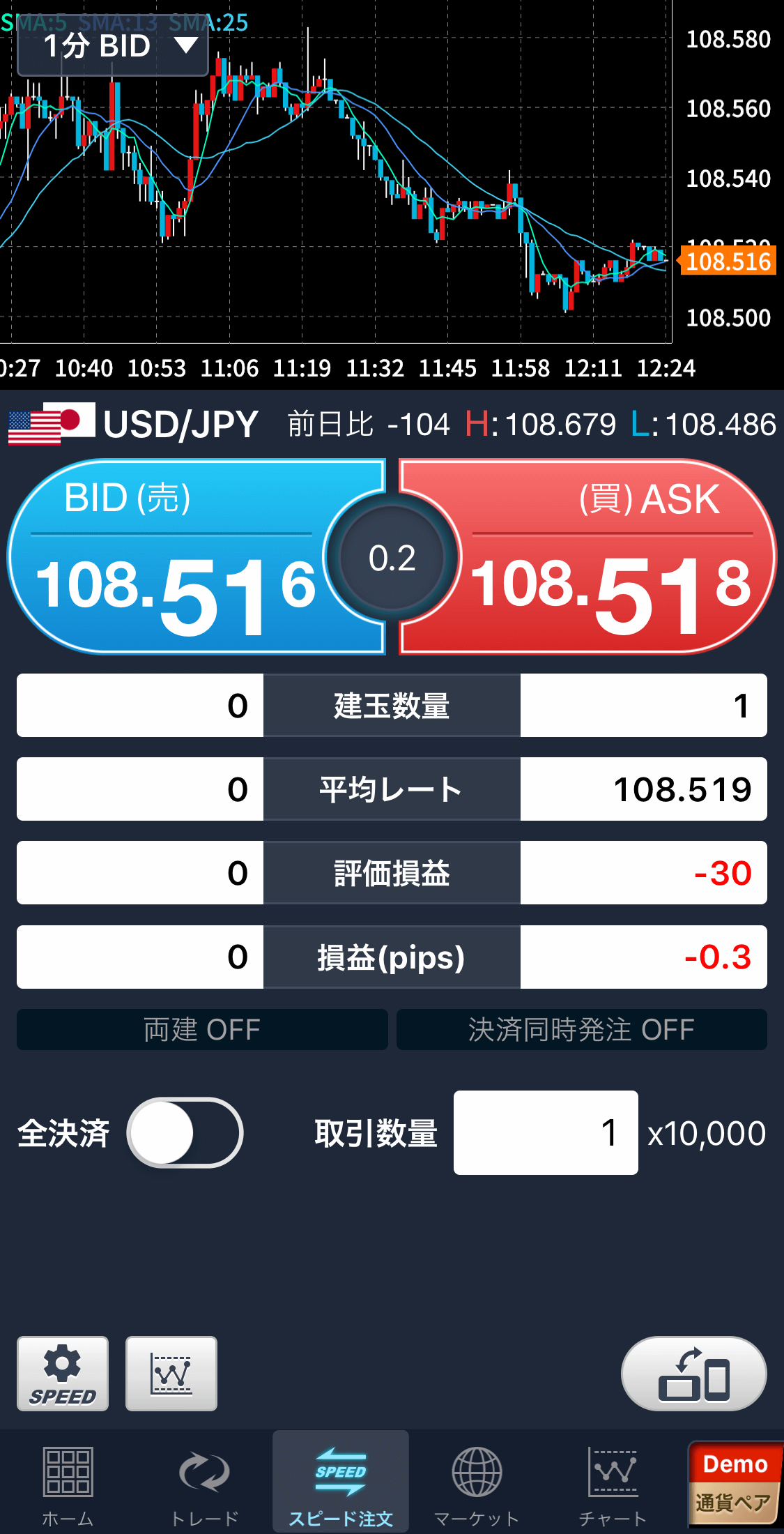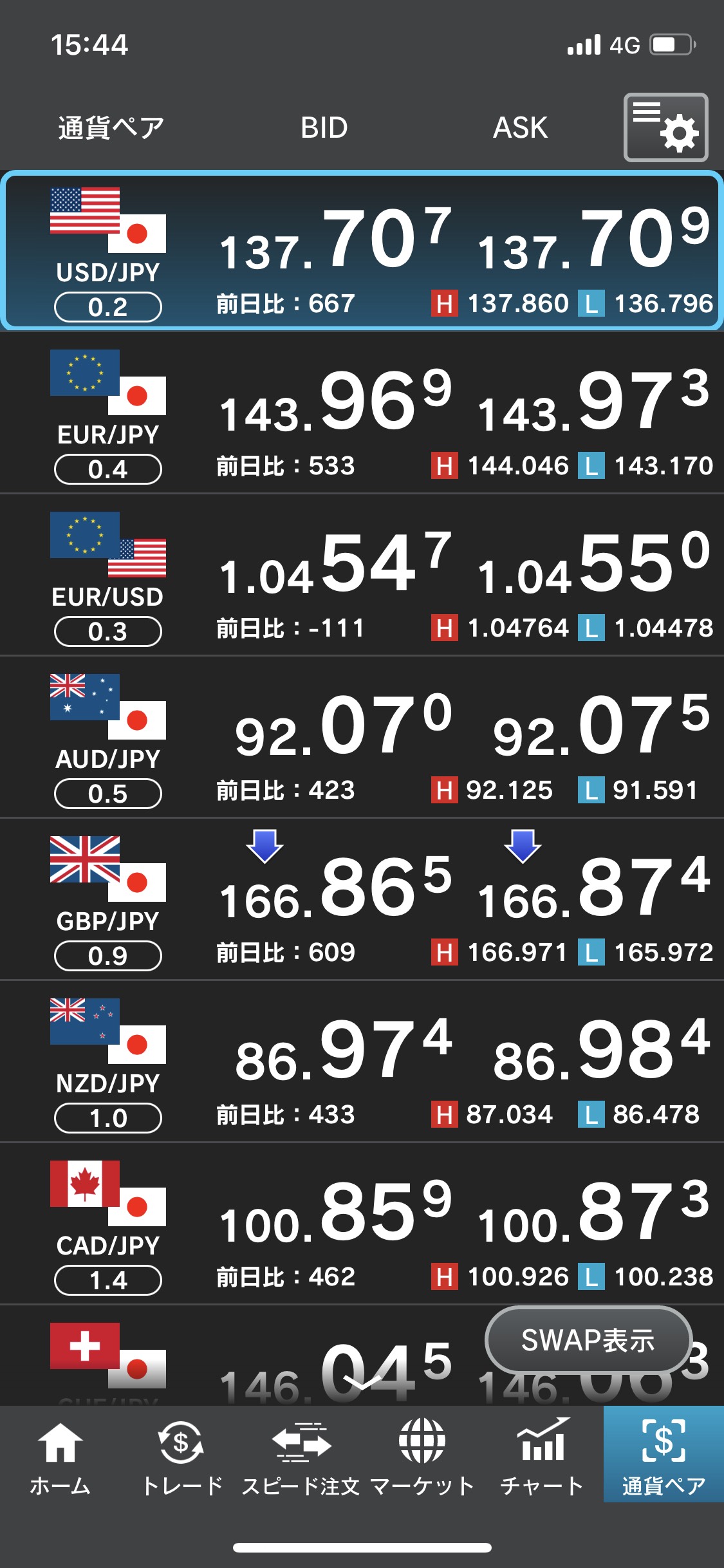【来週の注目材料】0.25%利下げは織り込み済み、ドットプロットに注目か=米連邦公開市場委員会(FOMC)
【来週の注目材料】0.25%利下げは織り込み済み、ドットプロットに注目か=米連邦公開市場委員会(FOMC)
来週16日、17日に米連邦公開市場委員会(FOMC)が開催されます(結果発表は日本時間18日午前3時)。
今年初となる利下げの実施がほぼ確実視されています。
前回7月29日、30日の米連邦公開市場委員会(FOMC)は市場予想通り5会合連続となる政策金利の据え置きとなりました。2名の理事が0.25%の利下げを主張して反対に回っています。地区連銀総裁ではなく、常任理事が2名反対に回るのは1993年12月以来34年ぶりとなりました。反対したのはウォラー理事(チーフエコノミスト)とボウマン理事(FRB副議長)です。なお、8月4日付で退任したクーグラー理事は欠席しています。次期FRB議長として名前の挙がるウォラー、ボウマン両名の利下げ主張もあって、追加利下げへの期待が広がりました。
前回のFOMC後、米雇用市場の厳しい状況が示されたことで、利下げ期待がさらに強まりました。8月1日に発表された7月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が予想を大きく下回ったことに加え、5月分と6月分が合わせて25万人以上の下方修正となり、雇用市場の厳しさが示されました。9月5日に発表された最新8月の米雇用統計でも非農業部門雇用者数が予想を下回る弱い伸びとなったことに加え、6月の数字がもう一段の下方修正でマイナス圏に落ち込みました。月次の雇用者数がマイナスとなるのは新型コロナのパンデミックで雇用市場が大荒れとなった2020年以来のことです。9月9日には米雇用統計、非農業雇用者数の年次改定暫定値が公表されました。米雇用統計のうち、非農業部門雇用者数などの事業所調査では、新たに誕生した企業による新規雇用は反映されず、事業閉鎖に伴う雇用者減も反映されないケースがあります。これらを暫定的に推計し、元の数字に調整を加えたものが今回の暫定値となります。さらに失業保険などの数字を基に実数値で数字を取り直したものが1月の雇用統計が発表される2月初めに示される確報値となります。事業閉鎖が多い景気の後退期には下方修正が多くなる傾向があります。今回は91.1万人と過去最大規模の下方修正となりました。昨年は81.8万人の下方修正が暫定値で示されていました(確報値では59.8万人に修正)。今回の対象となる2024年4月から2025年3月の期間に約180万人の雇用増が示されていましたが、暫定値ベースとはいえ約半分の雇用増であったということになります。こちらも雇用市場の厳しい状況を示す形で利下げ期待につながりました。
10日に発表された8月の米生産者物価指数(PPI)も利下げ期待につながっています。PPIは前月比が予想外のマイナスとなる-0.1%。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコアの前月比も-0.1%となりました。ともに予想は+0.3%となっていました。予想以上の伸びで市場の過度な利下げ期待を押し下げた7月の数字は、総合、コア共に+0.9%から+0.7%に下方修正されています。前年比は+2.6%と市場予想の+3.3%を大きく下回る伸び、7月の数字は+3.1%と+3.3%から下方修正です。コア前年比は+2.8%、こちらも市場予想の+3.5%を大きく下回りました。7月は+3.4%と+3.7%から下方修正されています。
前月比の内訳をみると、コア財が+0.3%と伸びる一方で、コアサービスが-0.2%となりました。関税の影響もあってコア財の価格が上昇も、サービス業が価格転嫁できていない状況が見られます。小売業と卸売業の利益率が1.7%低下しており、これは2009年以降で最大の低下率です。
物価が上昇していないこと、需要の減退が企業に厳しい状況となっていることなどから、景気支援での利下げに向けた期待が強まる形となりました。なお、この結果を受けてトランプ大統領は自身のSNSで「速報:インフレ無し!」と表記し、パウエル議長に利下げを求める姿勢を示しました。
11日に発表された米消費者物価指数(CPI)は総合の前月比の伸びがやや強かったものの、他はほぼ予想通りとなりました。前月比の伸びもガソリン価格が+1.9%と予想以上に伸びていたことが要因で、市場の影響は限定的となりました。ガソリン価格は米エネルギー情報局(EIA)の調査ベースではほぼ横ばいでしたが、対象地域の違うCPIで少し伸びていたものです(EIAは全米ベース、CPIは都市部のみのデータ)。
こうした状況を受けての今回のFOMCですが、0.25%利下げがほぼ確実視されています。前回0.25%利下げを主張した2名の理事や、退任したクーグラー理事の後任として15日に上院の承認採決を受けるミラン大統領経済諮問委員会(CEA)委員長がもし間に合った場合(FOMCは16日からなのでぎりぎり可能性があります)は0.5%の利下げを主張してくる可能性がありますが、多数派になる可能性はほぼないとみられています。
市場の注目は利下げ自体よりも今後の動き。今回は四半期に一度のメンバーによる経済見通し(SEP)が発表される回に当たっており、その中で示されるドットプロットでの年末時点での政策金利水準見通しが注目されています。
6月のFOMCで示された前回のSEPでのドットプロットは、年内2回の利下げが中央値でしたが、19名中7名が現行の4.25-4.50%に据え置きとの見通しを示し、2名が1回の利下げを示しました。今回利下げがほぼ確実のため、7名については確実に見方が修正されます。今回含めて3回、水準にして3.50-3.75%が中央値になるとの見方が大勢。19名(ミラン氏が間に合わなければ18名)のうち、何名が3回もしくはそれ以上の利下げを示すのかがポイントとなります。また、現状の厳しい雇用情勢を受けて2026年に入っても利下げが継続する可能性が意識されています。前回は3.50-3.75%が中央値となっていました。現在金利先物市場では今年の年末までに3.50-3.745%とした後、来年3回の利下げを行って2.75-3.00%とする見方が大勢となっています。ドットプロットでどこまで来年の利下げ見通しを強めてくるかが注目されます。市場の見通しに近いところまでの大きな修正が入ると、ドル売りが強まる可能性があります。
執筆者 : MINKABU PRESS
資産形成情報メディア「みんかぶ」や、投資家向け情報メディア「株探」を中心に、マーケット情報や株・FXなどの金融商品の記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコンテンツなど幅広く提供しています。